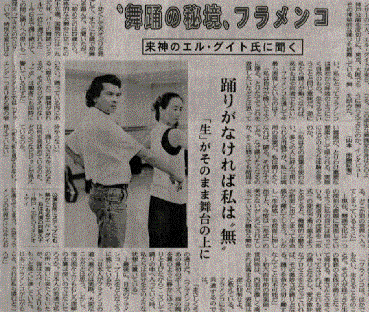|
|
||
|
”舞踊の秘境” フラメンコ 来神のエル・グイト氏に聞く スペインを代表するフラメンコ・ダンサーの一人、エル・グイトが来日、神戸公演を皮切りに、東京、大阪でも |
||
|
|
- 幼くして天才ぶりを発揮して、 すでに7歳で初舞台を踏んだ、と 聞いたが。 「始めたのは4歳から。本格的な 大舞台に立ったのは15歳。国際 的には1959年、パリの舞踊コンク ールで1位に選ばれた」 -今日まで踊り続けて、その間に - フラメンコを通して今最も表現 |
|
|
|
||
| - フラメンコでは「ドゥエンデ」つまりある種の暗い霊感が、とりわけ重要な要素として語られる。実際にはどのような体験をいうのか。 「私はその言葉を使わない。多くの人に好んで用いられる用語だが、私には無用の言葉だ。私は踊りたくなれば踊る。それがすべてだ。なぜ踊りたくなるのか、そこは問うても結局はわからない」 - 踊りのさなかにあなたは何を見詰めているのか。どのようなビジョンが見えているか。 |
- 現在、舞踊文化は一つの深刻な課題に直面しているように私の目には映っている。想像力の沈滞を「形式」の変化で乗り越えようと企てると、機械的な動きが前面に出てしまって、生命感から離れてしまう。しかし「生命感」を前面に押し出すと、今度は「形式」の美がないがしろにされてしまっていささか醜怪な舞台に落ちてしまう。ただフラメンコの世界だけは今なお両者の統一を保っているように見受けられるが・・・。 「フラメンコはほかでもない、生きることそのことだ。その人が経てきた生の軌跡の全体が踊りとなって現れる。奥さんとうまくいってなければ、それも彼の踊りとなるし、アイが微妙なプロセスをたどっていれば、その微妙さが踊りとなる。踊りを命から切り離すことなんてことは不可能だ」 |
- 約600年前の能楽師・世阿弥は 内面が激しく高まれば高まるほど、 表現は逆に抑制せよ、と教えている フラメンコにも共通するのでは。 「まさしくその通りだ。(フラメンコの あの最初ポーズ、両の腕を翼のよう に静かにゆっくりと上げながら)こうし て踊りの中へ入っていく時、私たち は自分をそのような状態に置いて いる」 - 最後に、日本のフラメンコ・ブー |
◂阿藤久子フラメンココンサート2001案内に戻る